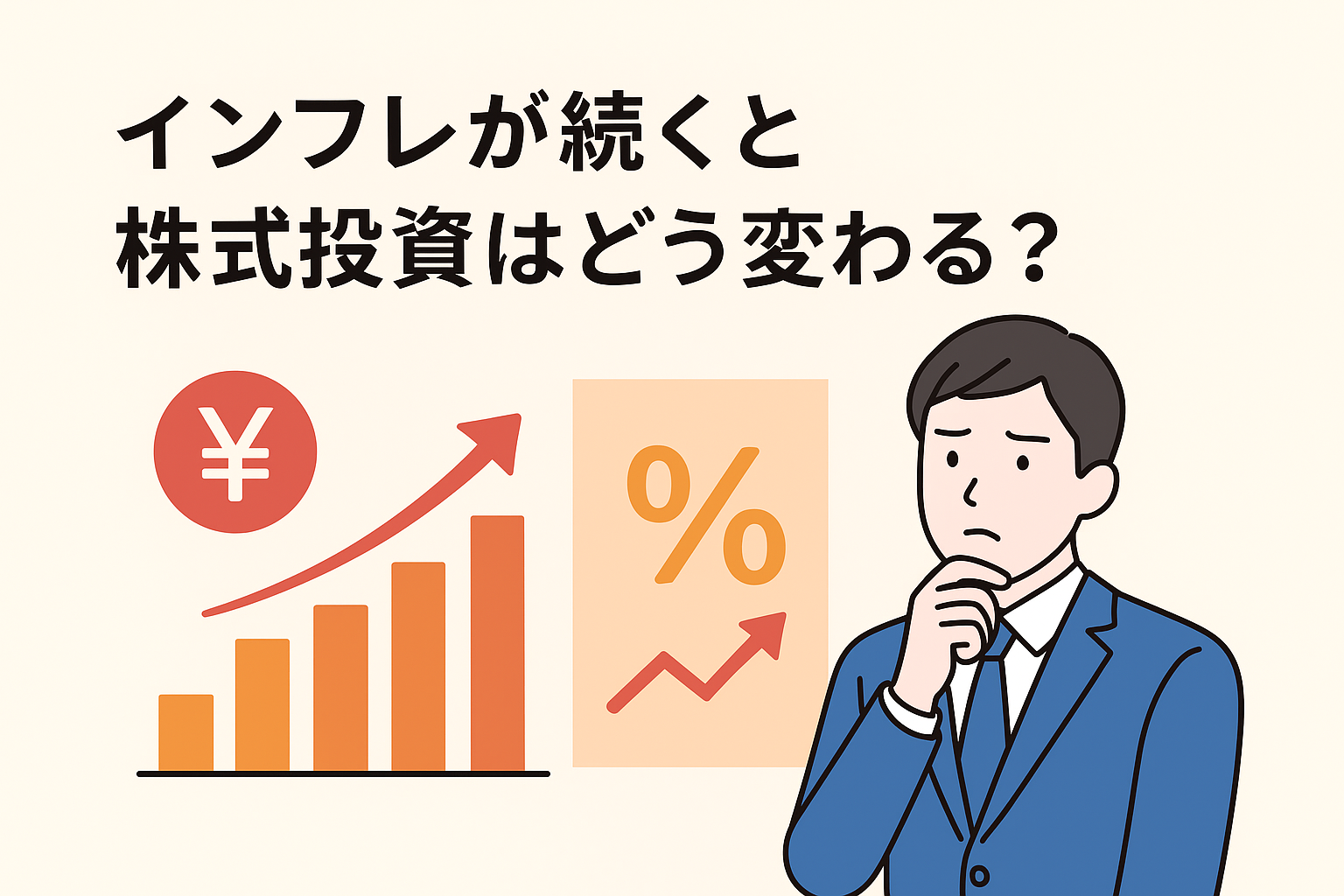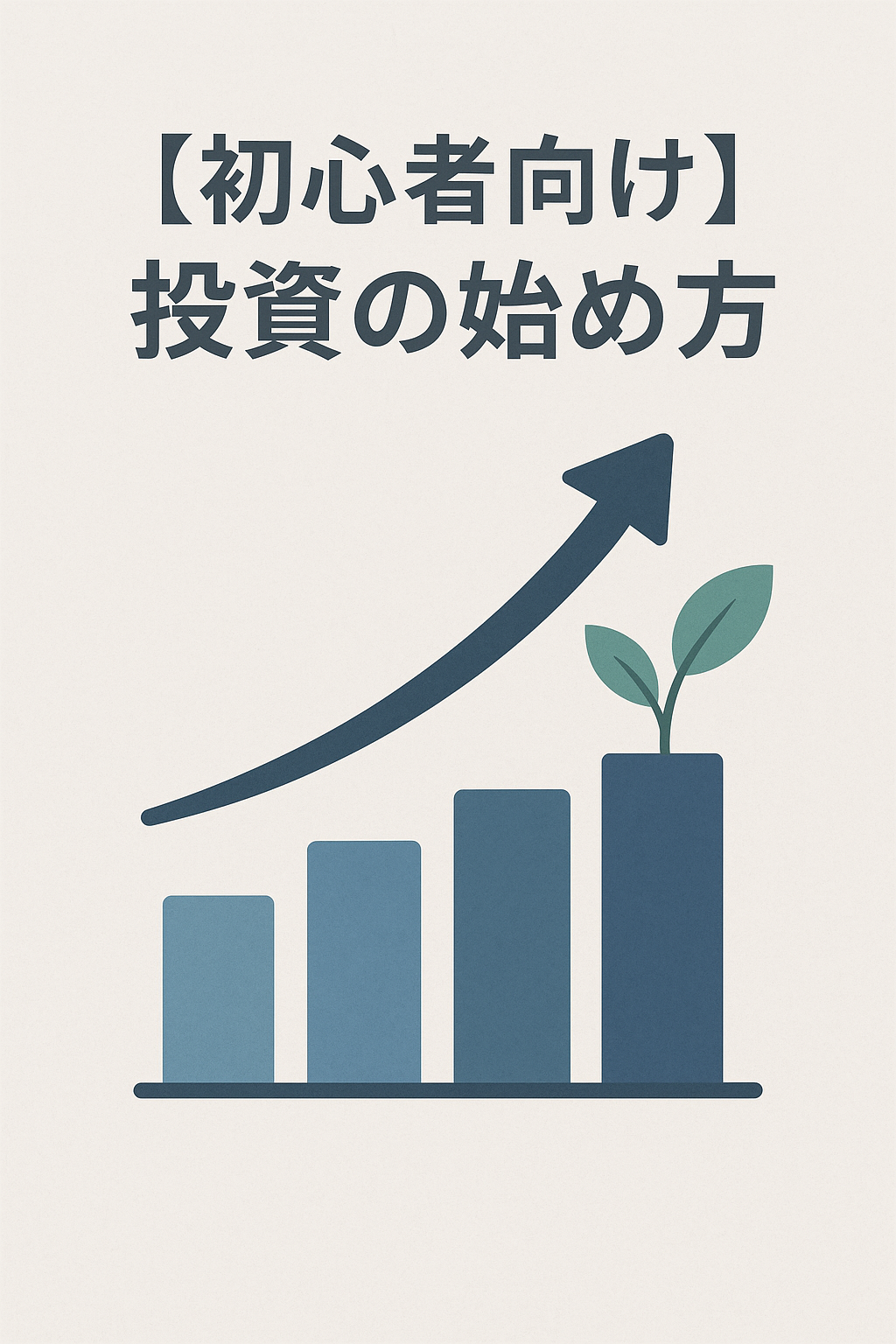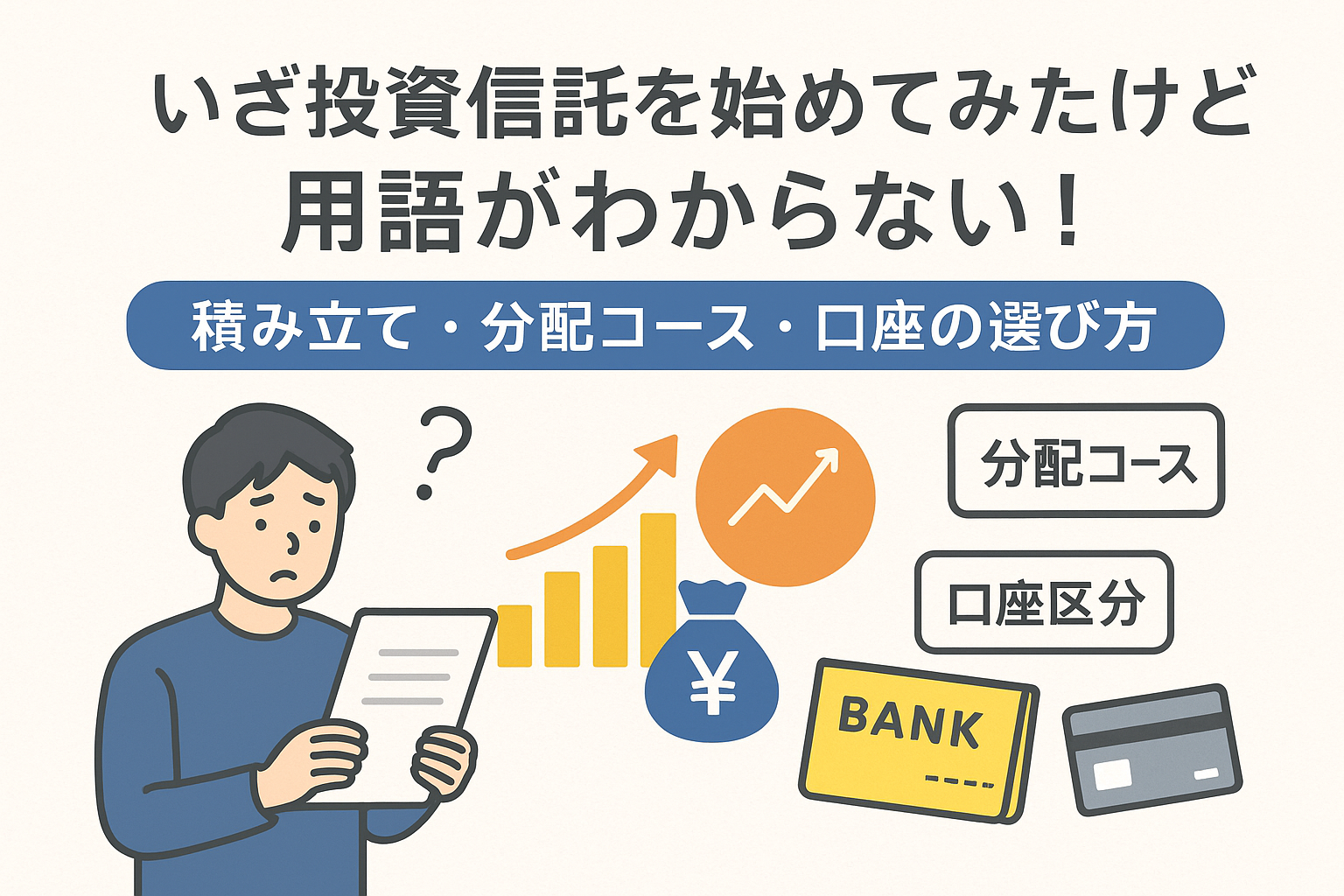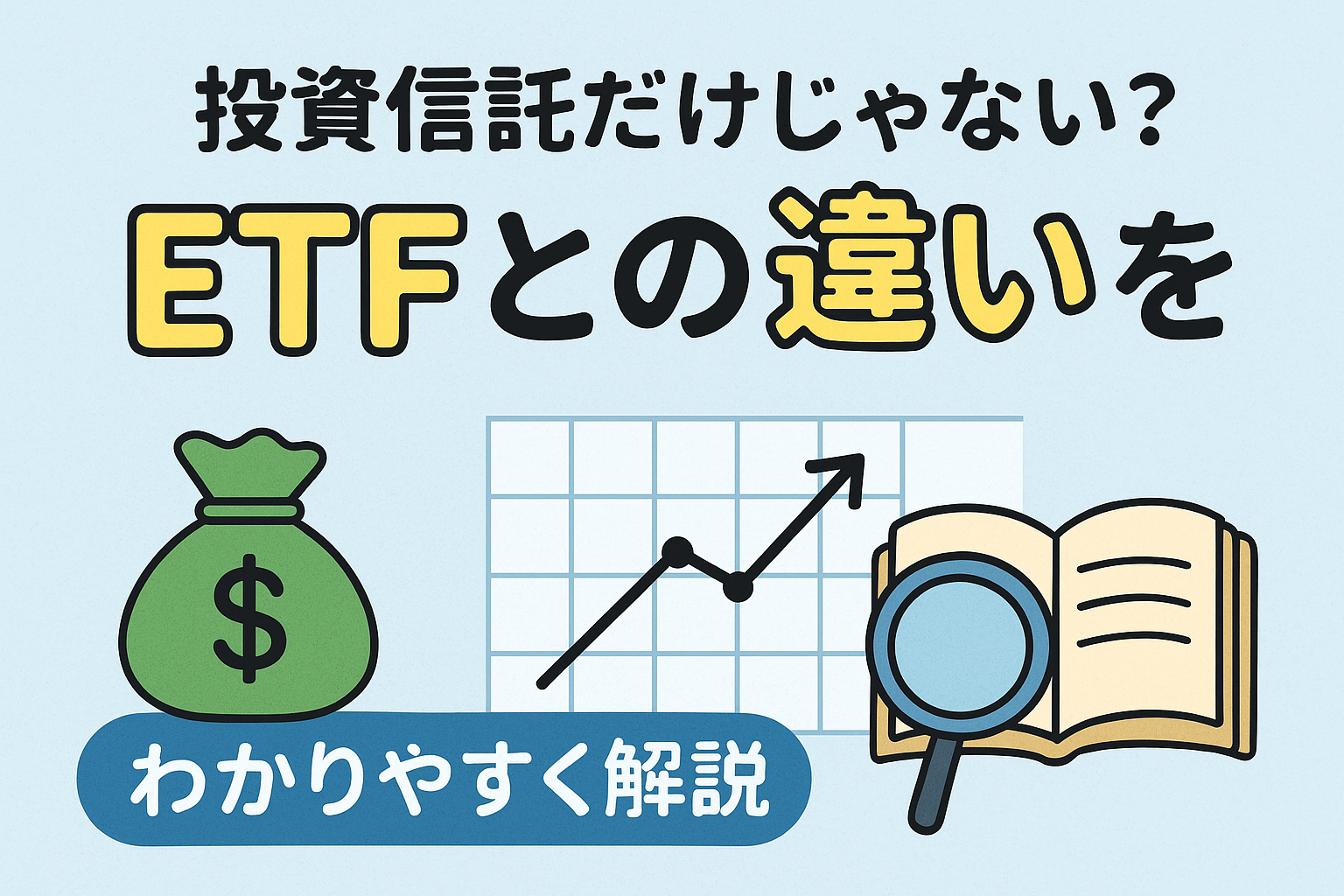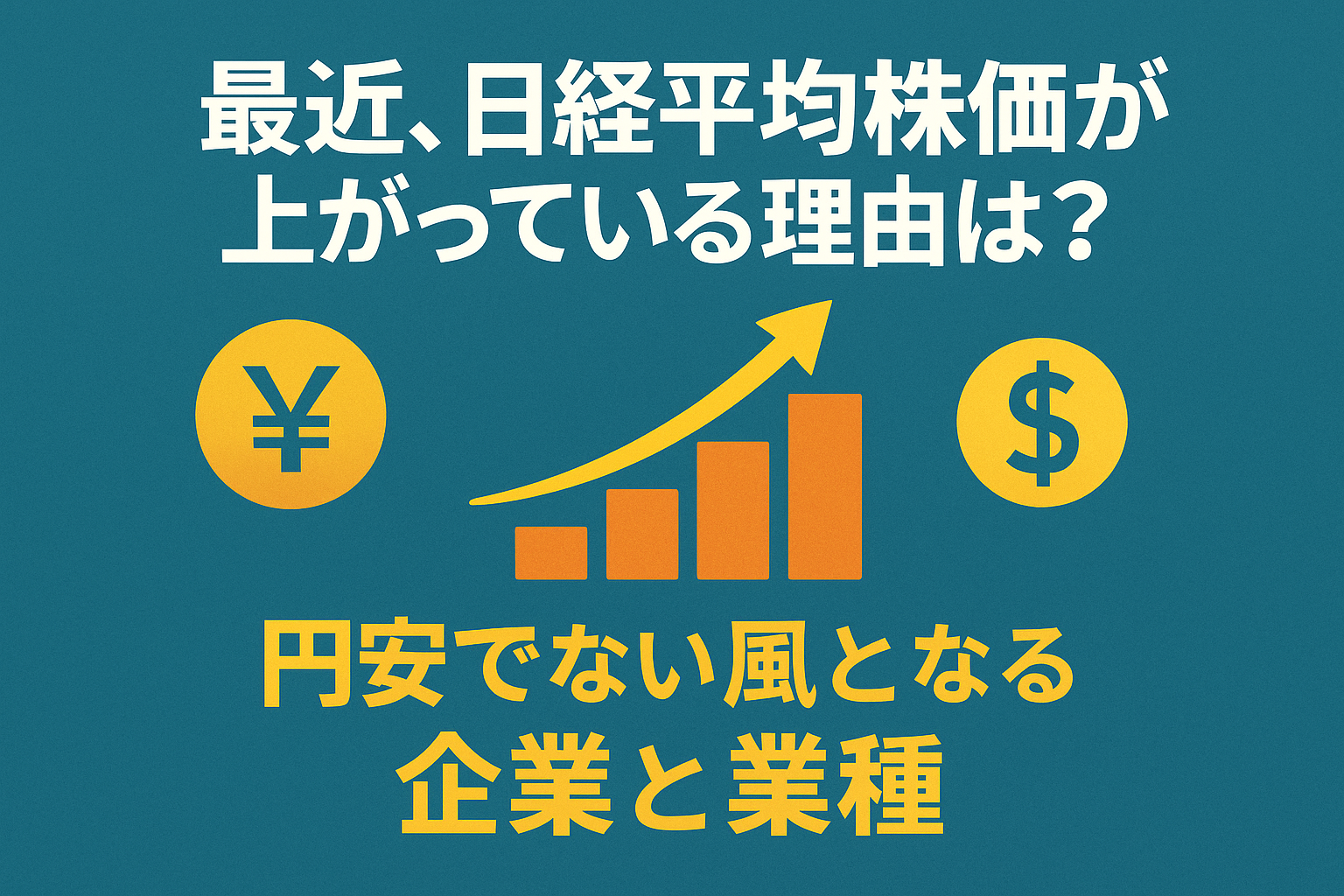インフレが続くと言われるけどインフレが続くと株式投資はどう変わる?
※この記事は投資の助言ではなく、一般的な知識の整理を目的としています。
インフレが続くと株式投資はどう変わる?
最近ニュースなどでも「物価上昇」「インフレが続く」といった言葉をよく聞きますよね。
では、インフレが続くと株式投資にはどんな影響があるのでしょうか?
実は、インフレは企業や投資家にとって「良い面」と「悪い面」の両方を持っています。
インフレが続くと何が起きるの?
インフレとは、モノやサービスの価格が全体的に上がっていくこと。
同じ1,000円でも、以前より買える量が減っていく状態です。
つまり、お金の価値が少しずつ下がるということになります。
政府や中央銀行が目指している「適度なインフレ(年2%前後)」なら経済が成長しているサインですが、
物価だけがどんどん上がって賃金が追いつかないような状態になると、家計にも企業にも負担になります。
インフレと株式投資の関係
① インフレが緩やかな場合
企業の売上が伸びやすくなり、株価にプラスの影響を与えることがあります。
物価上昇とともに企業が値上げできれば、利益が増えるからです。
② インフレが高すぎる場合
一方で、急激なインフレになると材料費や人件費が上がりすぎて、企業の利益を圧迫します。
さらに、中央銀行(日銀など)が物価を抑えるために金利を上げると、資金調達コストも増えます。
このような環境では株価が下がりやすくなることもあります。
インフレが続くと有利になりやすい業界
① 資源・エネルギー関連
インフレの中では、原油・ガス・鉱物などの価格が上昇しやすくなります。
そのため、資源価格の上昇が利益につながる企業は比較的有利です。
日本では例えばINPEX(1605)、ENEOSホールディングス(5020)などが代表的です。
② 金融業界(銀行など)
金利が上がると、銀行の貸出金利と預金金利の差(利ざや)が広がりやすくなります。
つまり、金利上昇=銀行の収益拡大につながる可能性があります。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)などがこの代表例です。
③ 不動産・リート関連
物価上昇とともに地価や賃料も上がる傾向があります。
そのため、三井不動産(8801)、三菱地所(8802)などの不動産やREIT(不動産投資信託)もインフレにある程度強い資産とされます。
ただし、金利上昇が急な場合は借入コストが増える点には注意が必要です。
逆にインフレが不利になりやすい業界
・電力・鉄道などの公共料金が固定されやすい業界は、コスト上昇をすぐに価格へ転嫁できないため不利です。
・すかいらーくホールディングス(3197)、吉野家ホールディングス(9861)、イオン(8267)などの人件費や原材料を多く使う外食・小売業界も、急激なインフレ時には利益が圧迫されやすくなります。
まとめ:インフレは「方向」よりも「スピード」が大事
- 適度なインフレは経済成長のサインで、企業にも追い風になることがある
- ただし、急激な物価上昇や金利上昇は株式市場のマイナス要因になりやすい
- 業界によってインフレへの耐性は異なる
インフレ局面では、どんな企業が値上げできるか、どの業界がコスト増に強いかを見極めるのがポイントです。
ニュースで「物価」や「金利」の話題を見かけたら、ぜひ自分のポートフォリオと照らし合わせてみてくださいね。